「本に囲まれて働ける仕事」や「一度は訪れたい」と言われるほど美しく芸術的な図書館が多く、憧れる人も多い図書司書。しかし、その実態は意外と知られていません。今回は、図書司書の仕事内容や雇用の現状、そして直面する課題について、一般の読者にもわかりやすく解説します。
図書司書の仕事内容とは?
図書館の仕事と聞くと、「本の貸し出し」「返却」「整理」といったイメージが強いかもしれません。しかし、実際にはそれだけではありません。図書司書の仕事には、以下のような業務があります。
- 利用者対応:本の貸し出しや返却の手続き、レファレンスサービス(調べ物のサポート)
- 資料の選定・管理:新しい本の購入、古くなった本の除籍(廃棄)
- イベント企画:読書会や講座の運営、子ども向けのおはなし会
- データベース管理:蔵書のデジタル化、システムの運用
- 広報活動:図書館のSNS運用や広報資料の作成
このように、図書司書の仕事は多岐にわたります。「ただ本を貸し出すだけ」と思われがちですが、利用者サービスの向上や資料の適切な管理など、専門的なスキルが求められる仕事です。
正規雇用への高いハードル
図書館で働くには、司書資格が必要なことが多いですが、資格を持っていても正規職員になれるとは限りません。むしろ、多くの図書司書は非正規雇用で働いています。
非正規雇用の現状
- 任期付き契約:多くの自治体の「公共図書館」では4割以上、学校図書館の職員の9割近くが1年ごとに契約される「会計年度任用職員」として働いている。
- 給与の低さ:フルタイムでも手取りが少なく、生活が厳しい場合も。
- 正規採用の狭き門:公立図書館の正規職員は少なく、募集があっても競争率が非常に高い。
特に自治体運営の公立図書館では、業務の外部委託が進み、派遣や指定管理者制度のもとで働く非正規職員が増加しています。その結果、「司書として働き続けたいのに、安定した職が得られない」という人が後を絶ちません。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/28fa0c16f7afc4619e24881ca821fcf1de331d19
司書業界が抱える課題
1. 人手不足と業務の多忙化
利用者サービスの向上が求められる一方で、非正規雇用の増加により人手不足が深刻化。少ない人員で多くの業務をこなさなければならず、業務負担が大きくなっています。
2. 図書館の予算削減
自治体の財政難により、図書館の運営費が削減されるケースが増えています。その影響で、新刊の購入が制限されたり、施設の維持管理が困難になったりすることも。
3. デジタル化の波
電子書籍やオンライン資料の普及により、図書館の役割も変化を求められています。しかし、デジタル化への対応が進んでいない図書館も多く、新しい時代に適応するための課題は山積みです。
それでも司書を目指す人へ
図書司書の仕事には厳しい現実もありますが、本が好きな人や、知識を求める人々のサポートをしたい人にとって、やりがいのある職業です。
もし司書を目指すなら、以下の点を意識すると良いでしょう。
- 正規雇用の募集を常にチェックする
- デジタル技術や情報管理スキルを身につける
- 図書館以外の職場(企業の情報管理など)も視野に入れる
「好きだからこそ続けたい」——そんな熱い思いを持つ人が、より良い環境で働けるよう、図書館業界全体の改革が求められています。
図書司書の現実を知った上で、それでもこの仕事に魅力を感じるなら、ぜひ挑戦してみてください!
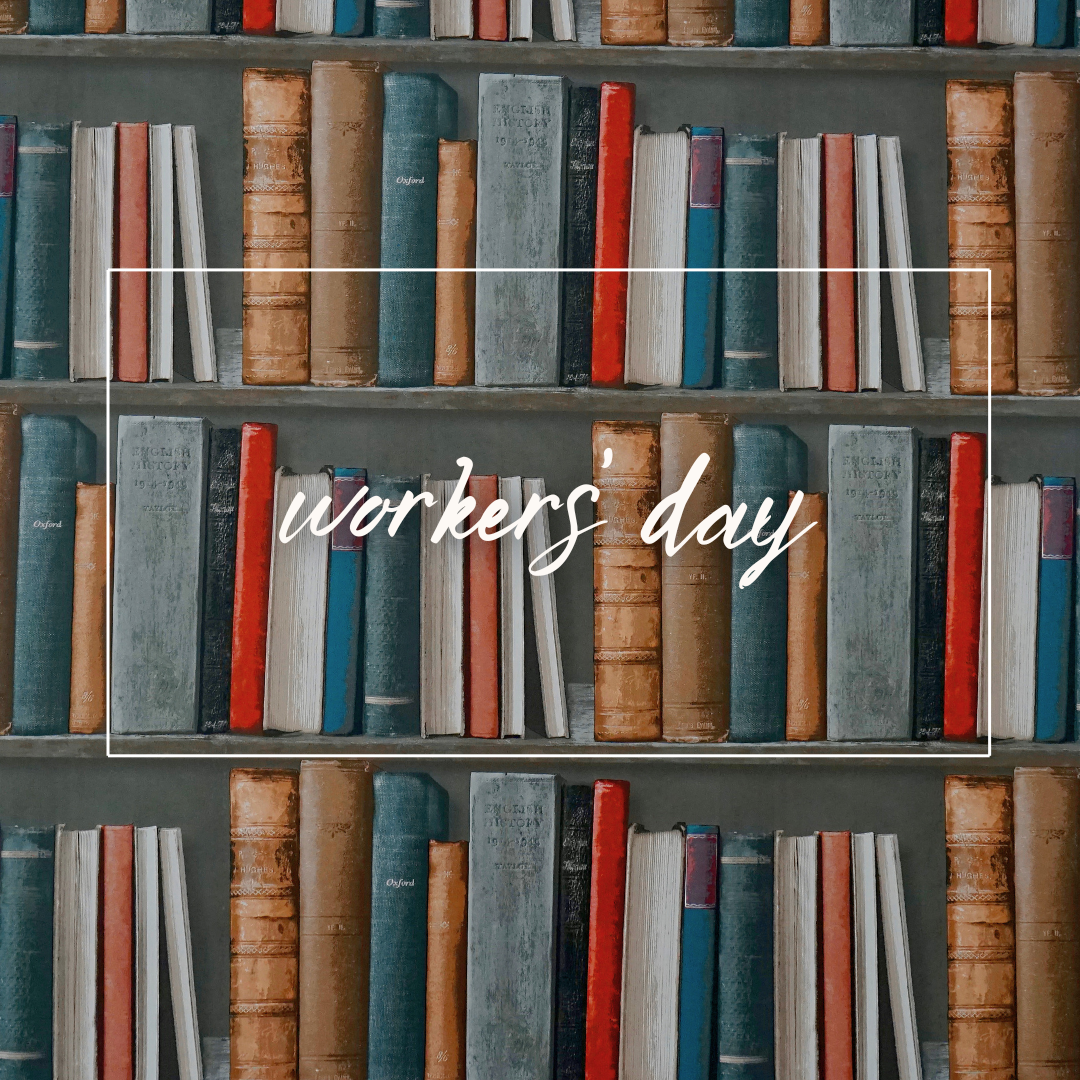


コメント